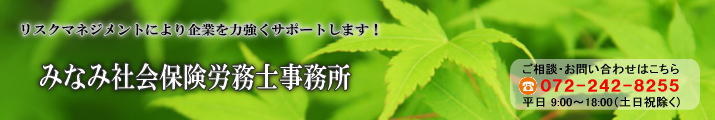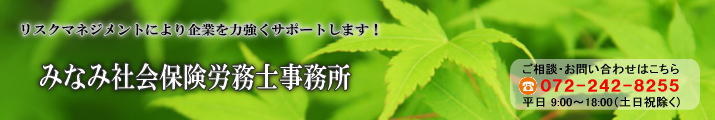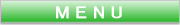
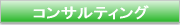

|
<事務所>
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256
|
|
|
|
|
HOME > 健康保険・厚生年金保険 > 社会保険の給付
<健康保険の給付>
1.療養の給付
被保険者の傷病に対して、現物給付たる「療養の給付」が行われます。
<一部負担金の割合>
| 年 齢 |
所得層 |
平成22年4月~平成23年3月 |
| 70歳以上 |
一定以上所得者 |
3割 |
| 一般所得者 |
1割 |
| 低所得者 |
| 70歳未満 |
- |
3割(義務養育就学前は2割) |
※一定以上所得者の要件
1)標準報酬月額が28万円以上であること
2)被保険者及び被扶養者の年収が520万円(被扶養者がいない者は383万円)以上であること
2.入院時食事療養費
被保険者が入院療養と併せて受けた食事療養(入院した場合の食事代)について支給されます。
<標準負担額>
| 区 分 |
標準負担額 |
| 一般の方 |
1食につき260円 |
| 市区町村民税非課税世帯の方 |
1食につき210円 |
| 市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
1食につき160円 |
| 市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者 |
1食につき100円 |
3.入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養)に要した費用について支給されます。
<標準負担額>
| 区 分 |
標準負担額 |
| 一般の方 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保健医療機関に入院している方 |
(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円 |
| 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保健医療機関に入院している方 |
(食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円 |
低所得者
(住民税非課税) |
低所得者Ⅱ |
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円 |
| 低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) |
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円 |
4.保険外併用療養費
保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
<評価療養>
先進医療
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬価基準収載前の承認医薬品の投与
保険適用前の承認医療機器の使用
薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
<選定療養>
特別の療養環境の提供
予約診療
時間外診療
200床以上の病院の未紹介患者の初診
200床以上の病院の再診
制限回数を超える医療行為
180日を超える入院
前歯部の材料差額
金属床総義歯
小児う触の治療後の継続管理
5.療養費
やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
①保険診療を受けるのが困難なとき
②やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
6.訪問看護療養費
居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。 訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっています。
7.移送費
被保険者が下記のいずれにも該当する場合、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用が支給されます。
①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
③緊急その他やむを得なかったこと
8.傷病手当金
被保険者が下記の要件を満たした場合、1日のつき標準報酬額の3分の2に相当する額が支給されます。任意継続被保険者に対する支給は廃止されました。(平成19年4月1日から)
①療養中であること
②労務に服することができないこと
③継続した3日間の待機を満たしたこと
9.埋葬料(埋葬費)
被保険者が死亡した時、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給されます。
死亡した被保険者に家族がいないような場合、埋葬を行った者に埋葬費として、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
10.出産育児一時金
被保険者が出産した時、1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっています。
※多児分娩の場合、胎児数に応じて支給。
※帝王切開等の異常分娩の場合も支給される。(この場合、療養の給付と出産育児一時金の両方が支給される)
11.出産手当金
被保険者が出産した時、出産の日以前42日から出産の後56日までの間において労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事をすることがあっても支給されます。
12.高額療養費
療養の給付、保険外併用療養費(差額部分を除く)、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費の支給を受けた際に支払った自己負担額が著しく高額であるときに支給されます。
※高額療養費算定基準額を超えた額が支給されます。(払い過ぎた分が戻ってくる)
<70歳未満の方の自己負担限度額>
| 所得区分 |
高額療養費算定基準額 |
| 上位所得者 ※1 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
【83,400円】 |
| 一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】 |
| 低所得者 ※2 |
35,400円
【24,600円】 |
※1 上位所得者とは、診療月の標準報酬額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者
※2 低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人
70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出することになります。
<70歳以上の方の自己負担限度額>
| 所得区分 |
高額療養費算定基準額 |
外来
(個人ごと) |
外来・入院
(世帯合算) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者(住民税非課税者等) |
Ⅱ ※1 |
8,000円 |
24,600円 |
| Ⅰ ※2 |
15,000円 |
※1 市(区)町村民税非課税者または低所得Ⅱの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者
※2 被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Ⅰの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合
13.高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。
※1 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※2 その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
<70歳未満の方>
| - |
所得区分 |
基準額 |
| ① |
被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合(上位所得者)
|
126万円 |
| ② |
①・③以外の場合(一般)
|
67万円 |
| ③ |
被保険者が市町村民税非課税の場合(低所得者)
|
34万円 |
<70歳~74歳の方>
| - |
所得区分 |
基準額 |
| ① |
高齢受給者証の負担割合が3割となっている場合(現役並み所得者)
|
67万円 |
| ② |
①・③・④以外の場合(一般)
|
56万円(※1) |
| ③ |
被保険者が市町村民税非課税の場合(低所得者Ⅱ)
|
31万円 |
| ④ |
③のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下(※2)の場合 (低所得者Ⅰ) |
19万円 |
※1 70~74歳の方の自己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記としています。
※2 年金収入80万円以下等
14.家族療養費
被扶養者について、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費と保険外併用療養費と同様の給付が行われるが、これらは全て家族療養費として支給されます。
15.家族訪問看護療養費
被扶養者が指定訪問看護を受けた時に支給されます。
16.家族移送費
被扶養者が家族療養費に係わる療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに支給されます。
17.家族埋葬料
被扶養者が死亡した時、被保険者に5万円が支給されます。
18.家族出産育児一時金
被扶養者が出産した時、1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)
<厚生年金の給付>
1.老齢厚生年金
1)65歳以上の支給要件
①厚生年金保険の被保険者期間(1月以上)を有すること
②65歳以上であること
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること)
<給付乗率>
| 被保険者期間 |
新給付乗率 |
| 平成15年3月まで |
1,000分の7.125
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の9.5~1,000分の7.23 |
| 平成15年4月以降 |
1,000分の5.481
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の7.308~1,000分の5.562 |
<平成12年改正前の従前額を最低保障することとなる場合の給付乗率>
| 被保険者期間 |
旧給付乗率 |
| 平成15年3月まで |
1,000分の7.5
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の10~1,000分の7.61 |
| 平成15年4月以降 |
1,000分の5.769
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の7.692~1,000分の5.854 |
<年金額>
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率
2)65歳未満の支給要件
昭和36年4月1日以前(女子は昭和41年4月1日以前)生まれの者について、65歳未満であっても下記のいづれにも該当する時、生年月日に応じ、所定の年齢から、定額部分が加算された、又は報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給される。
①原則として60歳以上であること
②厚生年金期間の被保険者期間が1年以上であること
③老齢厚生年金の受給資格期間(老齢基礎年金の受給資格期間)を満たしていること
<年金額>
定額部分(1階部分、65歳以降の基礎年金に相当)
1,676円×(1~1.875)×被保険者期間の月数(上限420~444月)×物価スライド率
報酬比例部分の年金額(2階部分、老齢厚生年金に相当)
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率
2.障害厚生年金
<支給要件>
1)被保険者要件
疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に係る初診日において被保険者であること。
2)障害の要件
障害認定日において、障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること。障害認定日とは下記の日をいいます。
①初診日から起算して1年6月を経過した日
②上記の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日
3)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていること。
<年金額>
A=平均標準報酬月額×給付乗率(老齢厚生年金と同じ)×被保険者期間の月数×物価スライド率
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
1級・・・A×1.25+配偶者加給年金額(+障害基礎年金+子の加算額)
2級・・・A+配偶者加給年金額(+障害基礎年金+子の加算額)
3級・・・A(最低補償額あり)
3.障害手当金
<支給要件>
下記の全ての要件を満たした場合、障害手当金が支給されます。
①疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に係る初診日において被保険者であり、その前日において保険料納付要件を満たしていること
②当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治っていること
③その傷病が治った日において、その傷病により厚生年金保険法施行令別表第2に示す障害の状態にあること
<支給額>
平均標準報酬月額×給付乗率(老齢厚生年金と同じ)×被保険者期間の月数×200/100
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
4.遺族厚生年金
<支給要件>
1)被保険者等要件
-短期要件-
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
-長期要件-
④老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
2)保険料納付要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていること。
<年金額>
-短期要件該当者-
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率×3/4
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
-長期要件該当者-
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率×3/4
※被保険者期間の月数は300月を最低保障なし、給付乗率の読替規定あり
5.脱退一時金
<支給要件>
厚生年金保険の被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者)は、次の全てを満たす時に請求することができます。
①老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること
②障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
③年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令を受ける者等でないこと
④日本国内に住所を有しないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
<支給額>
被保険者期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に下記に定める率を乗じて得た額が支給されます。
| 厚生年金保険の被保険者であった期間 |
率 |
| 6月以上12月未満 |
0.4 |
| 12月以上18月未満 |
0.8 |
| 18月以上24月未満 |
1.2 |
| 24月以上30月未満 |
1.6 |
| 30月以上36月未満 |
2.0 |
| 36月以上 |
2.4 |
|
|